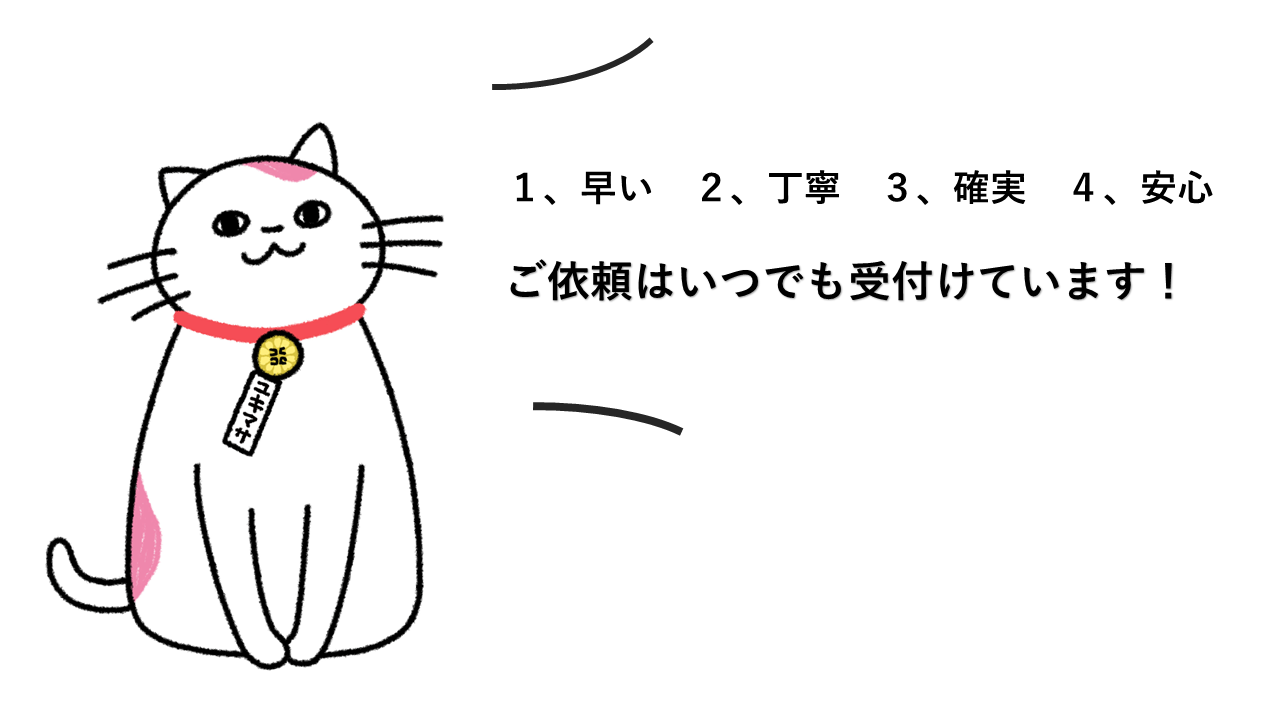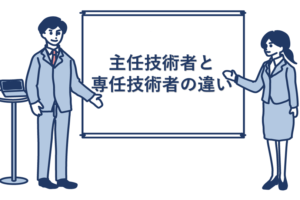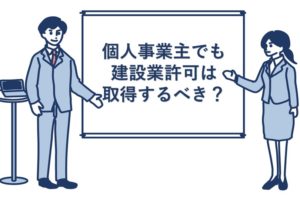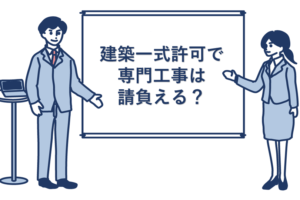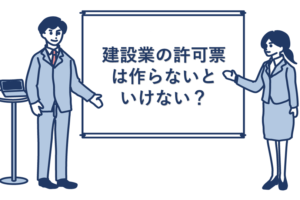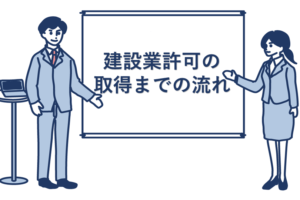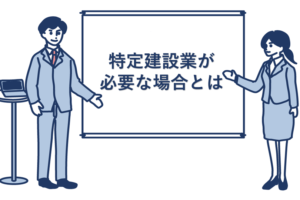建設業法違反をすると、「罰則」「監督処分」を受けることになります。
もしそれが処分が「罰金」以上になる場合だと、建設業許可の取消し処分にまで発展します。
建設業許可の取消し処分を受けると、再び度建設業許可を取得しようとしても、5年以上経過しないと取得できなくなりますので、かなり厳しい処分となります。
本記事では、この建設業法違反と罰則等の処分について解説していきます。
解説は建設業許可を専門としている行政書士がします。
目次
建設業法の立法目的とは?
建設業法の違反について知るためには、まず建設業法の立法の趣旨と目的について理解する必要があります。
建設業法の目的は、主に次の4つの事柄とまります。
- 建設工事の適正な施工を確保すること
- 発注者を保護すること
- 建設業の健全な発達を促進すること
- 公共の福祉の増進に寄与すること
建設業法の各規定は、これらの目的を達成するために設けられています。
つまり、この目的に沿わない行為は、処分の対象として挙げられているということになります。
建設業を営むならば、これら4つの目的はしっかりと把握しておく必要があります。
建設業法違反の罰則と監督処分とは?

罰則、監督処分の対象者は違反を行った対象者だけでなく、違反者が所属する法人や個人事業主も対象者となります。
罰則の重さは、当然のことながら違反によって異なります。
罰則は一番重たいもので3年以下の懲役又は300万円以下の罰金があり、一番軽いもので10万円以下の過料があります。
建設業法違反による罰則とは?
法令の違反に対し,刑罰あるいは行政罰を科することを定める規定となります。
罰則には、罰金、過料があります。
罰金
罰金とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰になります。
過料
過料とは金銭を徴収する制裁の一種になります。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではありません。
建設業法違反よる監督処分とは?
建設業者が、建設業法により課せられた義務を履行しない場合や規定に違反した場合には、刑罰とは別に監督行政庁による監督処分が用意されています。
監督処分の種類は次の通りとなります。
指示処分
建設業法に違反すると指示処分の対象となります。指示処分とは法令違反を是正するために監督行政庁が行う命令のことをいいます。
営業停止処分
指示処分に従わない場合は、営業停止処分の対象となります。指示処分なしで直接営業処分停止処分となることもあります。営業停止処分は1年以内の期間内が目安となります。
許可取消処分
不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、許可取消処分の対象となります。情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。
建設業法の違反行為と罰則

一番重いものでも無許可営業の3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条違反)
1.無許可で営業した場合
2.下請契約の制限を超えて営業した場合
3.営業停止中に営業した場合
4.虚偽、不正の事実に基づいて許可を受けた場合
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(建設業法第50条違反)
1.許可申請書等を虚偽申請した場合
2.変更等の届出を提出しなかった場合
3.経営状況分析、経営規模等評価を虚偽申請した場合
100万円以下の罰金(建設業法第52条違反)
1.工事現場に主任技術者や監理技術者を置かなかった場合
2.営業停止や許可取消の処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった場合
3.行政庁の必要な要求に対応しなかった場合
4.行政庁の要求に対して検査を拒み、妨げ、忌避した場合
10万円以下の過料(建設業法第55条違反)
1.廃業等の届出を怠った場合
2.調停の出頭の要求に応じなかった場合
3.店舗や現場に標識を掲げない場合
4.無許可業者が許可業者であると誤認されるおそれのある表示をした場合
5.帳簿を備えなかったり、虚偽の記載の記載をした場合
建設業許可の欠格要件に該当するとどうなる?

建設業許可には欠格事由と言うものがあります。
罰金以上の罰則を受けると、許可の取消しはもちろん、罰則後5年以上経過しないと許可を取得できなくなってしまいます。
これは建設業許可の取得要件の、「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者」に該当するためです。(⇒欠格要件について解説)
つまり、許可の取消し後に再起をはかろうにも、5年は長すぎるのです。
このように、欠格要件による処分は、かなり厳しい罰則になっていますので、そうならないためにも、建設業法遵守を心がけなくてはなりません。
建設業法違反での処分事例
実際にあった建設業法違反での処分事例です。
過去にどういったケースで処分が下されるか、事例を知ることで建設業法違反の対策が取りやすくなるために、参考として紹介します。
実際にあった違反に対する処分事例
指示処分
株式会社S工務店|建設業法第28条第1項第3号違反
当該建設業者の取締役が、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。
許可の取消し
株式会社S|建設業法第29条第1項第2号違反
当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金の刑に処せられた。
許可の取消し
F株式会社|建設業法第29条第1項第2号
当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金の刑に処せられた。
7日間営業停止
D工業株式会社|建設業法第28条第3項違反
当該建設業者は、羽曳野市発注の工事において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。
指示処分
T機工株式会社|建設業法第28条第1項第3号違反
当該建設業者が、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、罰金の刑に処せられた。
許可の取消し
株式会社P|建設業法第29条第1項第2号違反
当該建設業者の取締役が、道路交通法違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられた。
建設業許可取得を依頼する
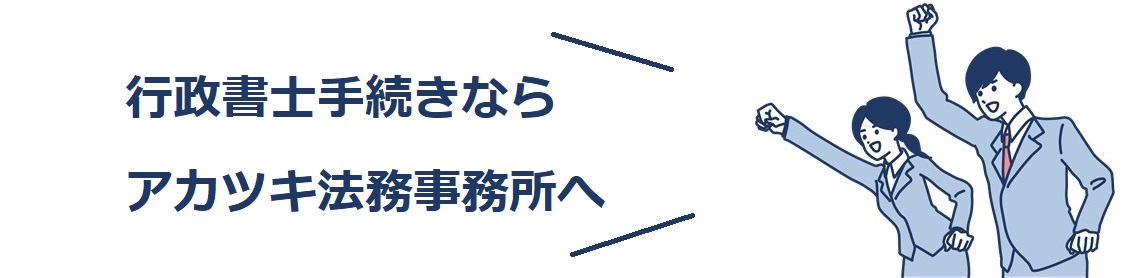
いかがだったでしょうか?建設業法の違反についての解説でした。
建設業許可を取得するためには、あらかじめ専門的な知識を習得しておく必要があります。
しかしながら、日々忙しい中で、これら専門的な知識を身につけるのは、簡単なことではありません。
そういった場合、専門的に手続きを行ってくれる行政書士事務所に依頼するのも一つの手かと思います。
当事務所に依頼すれば、法律的なアドバイスも含め面倒な申請も一任で行わせていただいております。
当事務所は、建設業許可の許可取得は数多くの実績があり、最も得意としているところです。
また、建設業許可の取得代行はもちろん、決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。
行政手続きのプロによる手続き代行を求めているのであれば、是非アカツキ法務事務所へお任せください。