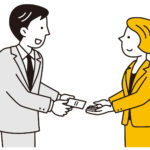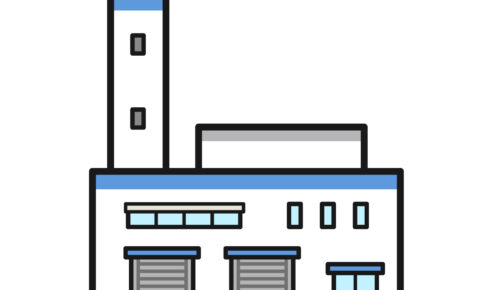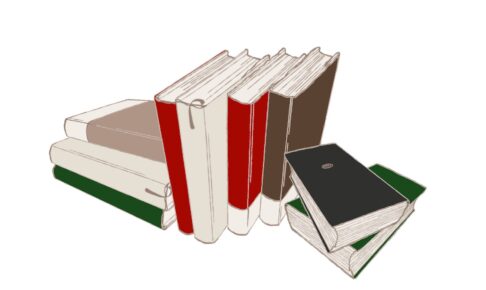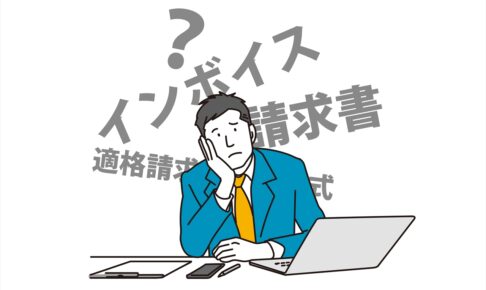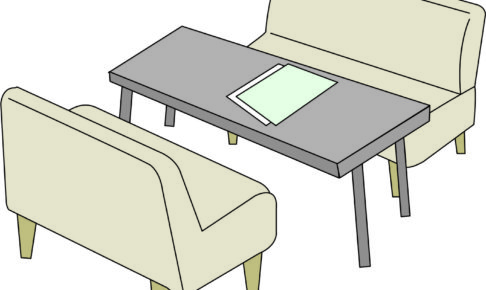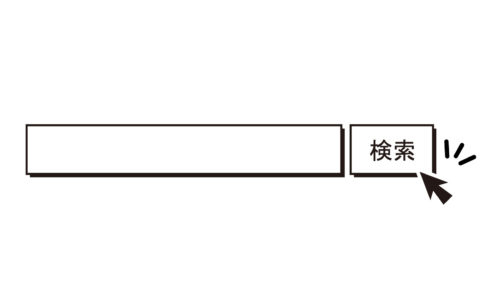行政書士は食えないとよく耳にしますが、行政書士は本当に食えないのでしょうか?
ネットやYoutubeで「行政書士 食えない」と検索すると、様々な情報が流れてきます。
いったいどれが本当なのでしょうか?
この記事では現役の行政書士が、「行政書士は食えない」について本音で実情を語っていきます。

行政書士は食えないは本当なのか?
ネットやYoutubeでもよく論争になっておりますが、行政書士は食えないは本当なのでしょうか?
結論からいいますと、「行政書士は食えない」は大部分の開業したての行政書士に当てはまります。
こう言い切ってしまうと、現在ご活躍されている行政書士の先生方に、怒られるかもしれませんが、事実そうです。
そもそも、食えるか食えないかという論争がなぜ起こるのか?というところにスポットをあててみます。
確かに他の士業でも食える食えない論争は少なからずありますが、行政書士だけそのコンテンツが突出して多いのが印象的です。
例えば、Youtubeもしかり、ネットやブログ、Twitterもしかり、「司法書士食えない」「社労士食えない」より「行政書士食えない」の方がコンテンツが多いのです。
そのことから導き出されることは、「行政書士は食えない」なのです。
もし、食えるのならそういった論争をする必要がない、というのが私の答えです。
「行書は食えない」コンテンツからみえてくるもの
先ほど、行政書士は食えないと言いましたが、全ての行政書士にあてはまるものではありません。
もちろん私も報酬をちゃんといただいて事務所を経営しております。
また、1,000万円以上稼いでいる先生方も私の周りには多くいらっしゃいます。
ではなぜ、「行政書士は食えない」論争が起きるのかというと以下の二つの勢力同士の論争だと考えられます。
二つの勢力
・行政書士を開業したが依頼がこなくて廃業した
・行政書士開業後に顧客獲得のため苦労した
依頼がこなくて廃業した派はもちろん食えていません。
それに対する顧客獲得のために苦労した派は、努力をして苦労したがゆえに私は食えているというコンテンツを出すのです。
これらコンテンツから見えてくる真理としては、食えるようになるには相応の努力をしないといけませんし、努力する量は他の士業よりも必要になるということです。
ちなみに、わたしも顧客獲得には大変苦労しましたし、食えるようになったからこの記事を書かさせていただいているのです。
なぜ行政書士は他の士業よりも努力が必要か?
それではなぜ、行政書士は他の士業よりも努力が必要なのか?
それは行政書士資格の構造的な問題もありますが、大きな要因として行政書士試験の難易度が他の士業より低いことがあげられます。
司法書士が3,000時間と言われている中、行政書士は1,000時間です。
果たして1,000時間の勉強量で専門性が身につくでしょうか?
また、行政書士試験の科目は実務とは直結しないものばかりなので、民法や憲法などの基礎法学的思考を手にいれたからといって、それがそのまま実務に生かせるかというと、そういった場面はほとんどありません。
そのため、他士業との勉強量の差を登録後に実務をこなしながら埋めていかなければならないのです。
実務ができないと営業が非常にやりずらい
なにせ、実務をやったことがないのに専門家として名刺に書き入れ、この仕事やれますとアピールしていかなければならないからです。
あなたにはできますか?
実務をやったことがないのに、専門家を名乗ることを?
こと、他士業に関しましては、実務の研修制度があったり、従業員の募集している事務所など少なからずあり、実務にふれる機会はあります。
そのため、実務を覚えてから自信をもって事務所を運営したい方によっては、他の事務所でしっかり経験を積んでから開業する道もあります。
しかし、行政書士の場合は他士業にくらべてかなり狭き門となります。
従業員の募集をしている行政書士事務所は数少ないですし、実務研修も一部の事務所が後進のためにと独自に門徒を開いている場合もありますが、大変珍しいケースで、特に実務に特化した研修はほぼありません。
そのため、新人行政書士は実務にふれることなく世にでることが常となります。
飯が食えるようになるまで5年間は耐えろ!?

私が行政書士に登録後、支部会の集まりに行って大先輩の先生に真っ先にいただいた言葉です。
飯が食えるようになるまで5年間は耐えろ!?と聞いて、どうとるかはあなた次第ではあると思います。
この言葉を聞いて、なにくそ!と営業に力を入れ5年も待たずして稼ぎまくっている同年代の先生もいれば、5年で足りるか?という先生もいます。
私がこの言葉を聞いて、まず初めに思ったのは「なんだ5年耐えたら飯が食えるんだ」です。
つまり、そのまま大先輩の先生の話を素直に聞き入れるなら、逆算からして5年耐えるだけで飯が食えるようになれる、ということです。
私はその言葉をいただいて、最初から覚悟はしておりました、やっぱり長期戦になるよね?と感じたのを覚えています。
「コネなし」「金なし」「経験なし」で始めるのですから、開業当初からバンバン依頼をとって稼いでいけるとは思ってはいなかったので、納得の言葉でもありました。
ただ、この5年というのは、人並みに営業し、実務を積んで5年です。
何もせずにただぽけーと事務所で待っているようでは、10年コースになってしまいます。
ただし、5年というのは長いようで、とても短いです。
耐えるといっても、営業も実務の勉強もしながらだと、あっという間に5年生になってしまいます。
しかも、この5年を耐えるだけで、死ぬまで行政書士として働けるのです。
昨今では年金問題など、行く先を不安に思う事は多々あります。
しかし、その不安を払拭する一つの方法として若いうちに自己投資して、死ぬまで働ける環境を作っておくことが大事だと思います。
もし、死ぬまで働けれる環境にいることができたら、金銭的な不安は少なからず払拭されます。
そのための今の5年は、私はとても短いものだと思います。
食えない期間を短縮することができる
前述では5年耐えろと言及しましたが、その人の才能や努力、開業前にすでにあった人脈など、その人の能力で、5年を3年に短縮できたり2年に短縮することができます。
行政書士業は客商売とはまた少し異なりますが、大きくカテゴライズさせると客商売みたいなものかもしれません。
お客さんにその人柄や仕事ぶりを気に入られて、また次の指名がくる。
そうやって新規開拓をしながら、リピート業務を稼いでいきます。
いわゆる人気商売なのです。
また、マーケティングの才能があれば新規顧客を獲得するのは他愛もないことですし、元々人脈がある人ににとっては紹介紹介で仕事が入ってきます。
そうして早い段階で実務を覚えてしまえば、鬼に金棒になります。
「実務ができ、かつ依頼が入ってくる」状態なのですから。
こうして、5年耐えないといけないところを3年に短縮することができたり、2年に短縮することができたり、することができるのです。
もちろん、5年を3年や2年に短縮させるのですから、それ相応の努力は必要になります。
食えない行政書士は廃業する!?

大部分の方が耐えることができずに脱落していくのですが、もちろん人にはそれぞれの事情があります。
家族がいる場合は家にお金をいれないといけない人もいます。
また、家賃や光熱費、人件費などランニングコストがかかり過ぎて赤字が膨らみ、やむなく廃業する人もいます。
しかしながら、開業前の5年間耐えうる事業計画や、それ相応の努力を欠くことによりこういった結果になるものだと考えられます。
実際私は10年間耐えに耐えてようやく花が開いたと喜んでおられる先生も知っております。
昔ながらに言う、士業とは年期ということなのです。
行政書士はさらに食えなくなるようになる!?
それでは、私が言うように、5年耐えれば安泰なのか?
行政書士に限らず、現在他士業でも登録者数が年々増えています。
私が試験勉強をし始めた10年前でさえ、士業は過当競争であると言われてきましたが、現在ではさらに競争が激化しています。
私は、まだまだ士業の数は増加の一途を辿ることになると予想しており、今後はさらに食えない行政書士が量産されていくと予想しています。
それは「行政書士は食えない」が5年間耐えろが、スタンダードだったところが、8年、10年になることを意味します。
流石に、8年、10年は短い期間だとは言い切れません。
そのため、行政書士で食いたいのであれば、先行者有利の権利をとるため、早め早めの参入が必要不可欠となります。