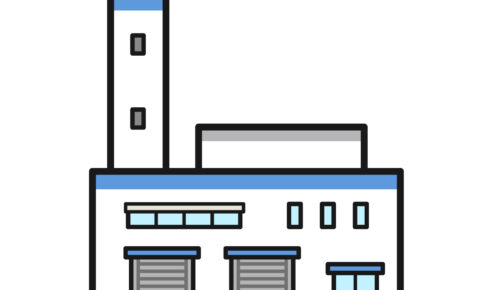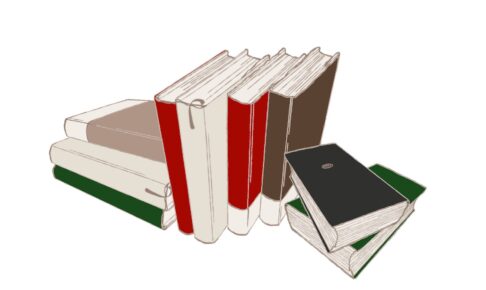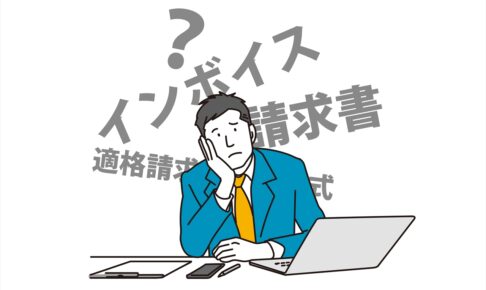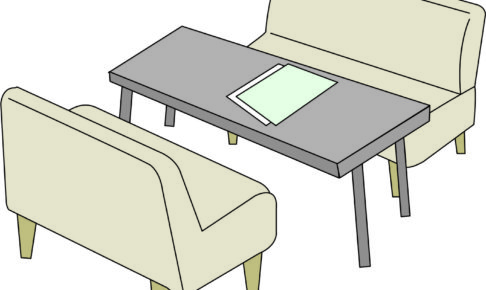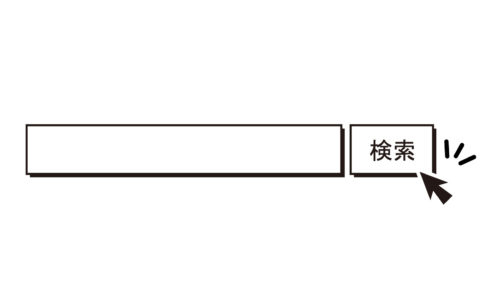行政書士の年収は、他士業の弁護士や税理士、社労士から比べると低くなっています。
行政書士は、8士業の一つとされており、先生業ではあるけれども、年収が伸びにくい業種となります。
また、年収でいえば、一般の会社員よりも年収が低く、年収だけ突出してみればなんだか残念な業種となります。
それでは、行政書士の年収はなぜ低いのでしょうか?
この記事ではこのことについて解説していきます。
データから見た行政書士の年収
行政書士会連合会がアンケートをした結果、行政書士業務の年間の売上高で500万円未満と答える行政書士は、全体の80%程となっておりました。
これは、売り上げの金額となりますので、経費を差っ引いた年収に直すと売上高6掛けで300万円程度となります。
つまり年収300万円に満たない行政書士が全体の8割程度だという事になります。
サラリーマンの平均年収が400万円以上あるなか、それよりもさらに低い水準となっています。
行政書士の年収はなぜ低い?

では、行政書士の年収はなぜ低いのでしょうか?
その理由として次の事由が考えられます。
・業務が幅広いから
・行政書士が多すぎる
・定年組行政書士が多いから
業務が幅広いから
先ず最初に挙げられるのが、業務範囲が他士業と違って幅広いからです。
業務が幅広いということは、なんでもできるということなので、なんでもできるということは専門性がないということになります。
専門性がなければ、報酬を上げることができなく、どうしても自由競争下で依頼を獲得していかなければなりません。
行政書士の代表的な業務は許認可業務ですが、許認可業務は決して難易度が低い業務ではありません。
難易度が低い業務の場合でしたら、流れ作業のようにこなしていけば採算性が合うかもしれませんが、一つ一つ注力が必要になる業務で価格競争をしていれば、採算が合わないのは歴然です。
それでは、業務をしぼって専門性を上げれば?という問いになるかもしれませんが、リピート性があって安定的に売り上げがつくれる、いわゆるおいしい分野は、もうすでに同業者にうめつくされています。
後発組である行政書士が、その分野に入り込んでいくには、かなりの努力が必要となります。
業務を絞り込むことができなければ、多分野に進出する必要性があるため、その分生産性はさがります。
行政書士が多すぎる
行政書士業務は、8士業の中の士業としての業務では、ニッチ業務であると言わざる負えないです。
なぜニッチ業務かというと、これは行政書士事務所を経営すればわかることだと思いますが、見込みとなる顧客の層のパイが、他士業がターゲットとしているパイとくらべ圧倒的に小さいからです。
許認可業務で例えるならば、行政書士が狙えるターゲットは許可が必要になる業種の事業者のみとなります。
税理士の場合、確定申告が必要になる事業者がターゲットとなるので、それに比べ狙えるパイはずいぶんと小さくなります。
つまり、需要は少ないのに、行政書士が多すぎるため、供給過多をおこしている状態にあります。
定年組行政書士が多いから
行政書士は、60代からでも開業できる業種ではあります。
年金を貰いながら、ボケ防止のために開業している行政書士も多数いらっしゃいます。
行政書士は、行政書士試験を受験して、資格の取得後開業するのが一般的ですが、ある一定数公務員として従事した方も開業することができます。
また、行政書士試験自体それほど難しい資格ではありませんので、開業するハードルがそれほど高くありません。
そのため、行政書士で本気で稼ごうとする人以外の方も安易に行政書士を開業することができ、全体の平均年収を下げる要因となっています。
よくある行政書士は稼げますよ!というコンテンツ
昨今では、Youtube等でよく見かけますが、行政書士は稼げます!というコンテンツ。
内容をみていれば、行政書士として行政書士業務で稼ぐといった趣旨のものではなく、行政書士の資格を活かして、こういったサービスを展開するというものばかりです。
また、顧客開拓のコンテンツもよくありますが、ある程度行政書士として営業はするべきですが、あまりにも過度な営業をする場合は、もう先生業とはいえないですし、行政書士以外の事業で営業をした方が、生産性は良いと思います。
たしかに、起業家とするならば、正解なのでしょうが、行政書士としてするならばいかがなものか?と感じる人は少なくないのではないしょうか。
まとめ
行政書士の年収はなぜ低いのかについてまとめると、直接的理由は、生産性が低くなりがちで、供給過多をおこしていることが挙げられ、間接的理由として開業しているだけの行政書士多く年収平均値を下げているという事になります。