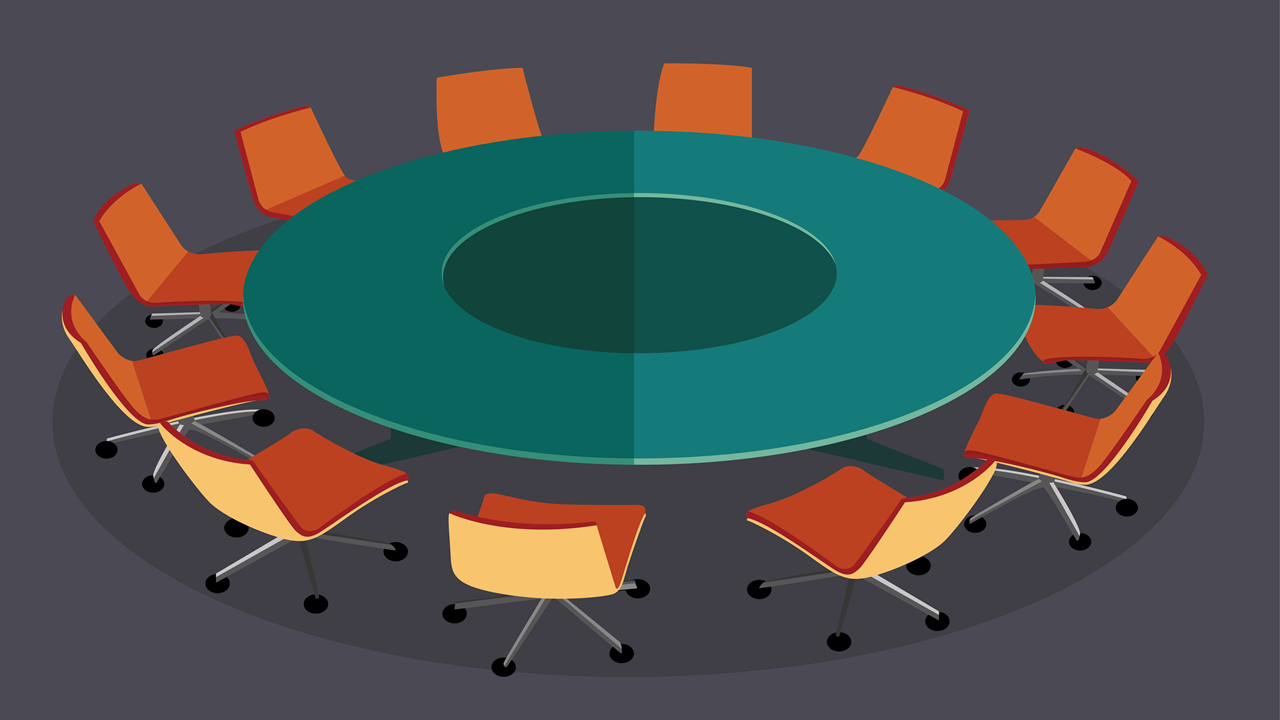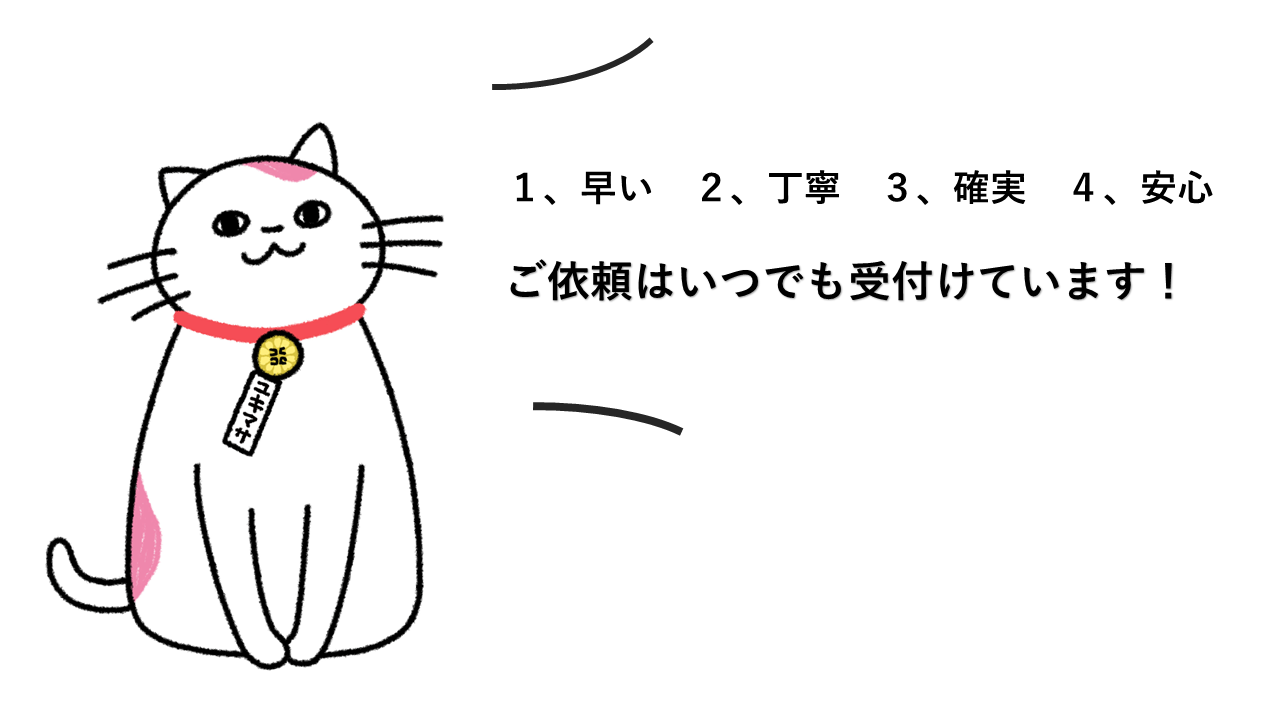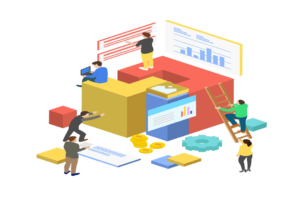株主総会は会社の組織の中の最高意思議決機関です。
本記事では、株式会社の株主総会について解説していきます。
目次
株主総会とは
株主総会とは会社の意思決定をするときの最高決定機関です。
株式会社の株主が集まり、定款の変更、資本の減少、会社の解散、合併、取締役や監査役の選解任、役員報酬などを決定したりします。
毎年、決算ごとに開催される定時総会と、何か問題などが起こった時に必要に応じて開く臨時総会があります。
株主は保有株式数に対応している議決権を持っており、株主たちの議決権の多数決によって決議されることとなります。
株主総会の決議の種類
株主総会の決議には普通決議、特別決議があります。
株主総会の普通決議では、株主総会の議長の選出、取締役、監査役の選任などができます。
この普通決議では総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成で成立します。
(※定款によって、この要件を変更することが可能。)
株主総会の特別決議は、定款変更、会社合併、株式併合、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めることができます。
この特別決議では、総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立します。
(※定款によって、過半数にあたる株式を有する株主を3分の1まで下げることが可能。)
一人株主総会
会社法の規定では、事業年度終了後3ヶ月以内に定時株主総会を開催しなければならないことになっています。
これは事業年度の決算の承認を要するためです。
計算書類の承認が株主総会でなされたら、法人としての税務申告をする必要があります。
つまり、会社の大小の規模に関わらず、一人株式会社であろうと必ず定時株主総会を開く必要があるのです。
株主総会議事録の作成
株主総会議事録とは、株主総会の議題と決定事項とその経緯を記録したものです。
株主総会を開催すれば必ず作成します。
議事録への義務付けられている記載記録事項を記載しなかったり、虚偽の記録を行えば、その作成者に対し罰則が科される場合もあるので注意が必要です。
しかし、株主総会議事録は、議事の経過や決議の結果が記録によって分かれば良いので、一文一句正確に記録する必要はありません。
結論さえ違わなければ、議論の概要の記録で構わないので、あまり神経質になって作成する必要はありません。
株主総会議事録の書き方
定時株主総会議事録
平成〇〇 年 〇 月 〇 日 午後3時00分
大阪府大阪市中央区〇〇町〇〇-〇〇において、定時株主総会を開催した。当日の出席株主数ならびに株式数は下記のとおり。
株主の総数 1名
発行済株式の総数 500株
議決権を行使できる株主の数 1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数 500個
出席株主数(委任状による者を含む) 1名
出席株主の議決権の数 500個
出席取締役及び監査役
代表取締役 暁一郎(議長兼議事録作成者)
取締役 大阪次郎、奈良三郎
監査役 兵庫四郎
定刻、代表取締役暁一郎は議長席に着き、定款により議長たることを述べ、本総会の開会を告げ、本日の出席株主数およびその持株数、議決権数を前記のとおり報告し、定足数を満たしているので本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議事に入った。
第1号議案 決算報告書の承認に関する件
議長は、当期(令和元年1月1日から令和2年12月31日まで)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ満場異議なくこれを承認可決した。
1 貸借対照表
2 損益計算書
3 株主資本等変動計算書
4 個別注記表
第2号議案 取締役及び監査役の任期満了に伴う改選に関する件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任することに可決確定した。
なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。
取締役 暁 一郎
取締役 大阪 次郎
取締役 奈良 三郎
監査役 兵庫 四郎
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後5時30分閉会を宣した。
上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。
平成〇〇 年 〇 月 〇 日
株式会社アカツキ 定時株主総会
代表取締役 暁 一郎 印
取締役 大阪 次郎 印
取締役 奈良 三郎 印
大阪で開業・起業支援サポートを依頼する
いかがだったでしょうか?株主総会の解説でした。(⇒定款作成ガイドに戻る)
アカツキ法務事務所では、会社設立や創業融資サポートなどの起業支援、営業に必要な許認可や外国人の就労ビザの取得代行など行っております。
また、他士業の専門業務に関しましても広く提携を結び、サービスを提供させていただいております。
ご依頼・ご相談に関しまして、お気軽にお問い合わせください。(⇒お問い合わせする)