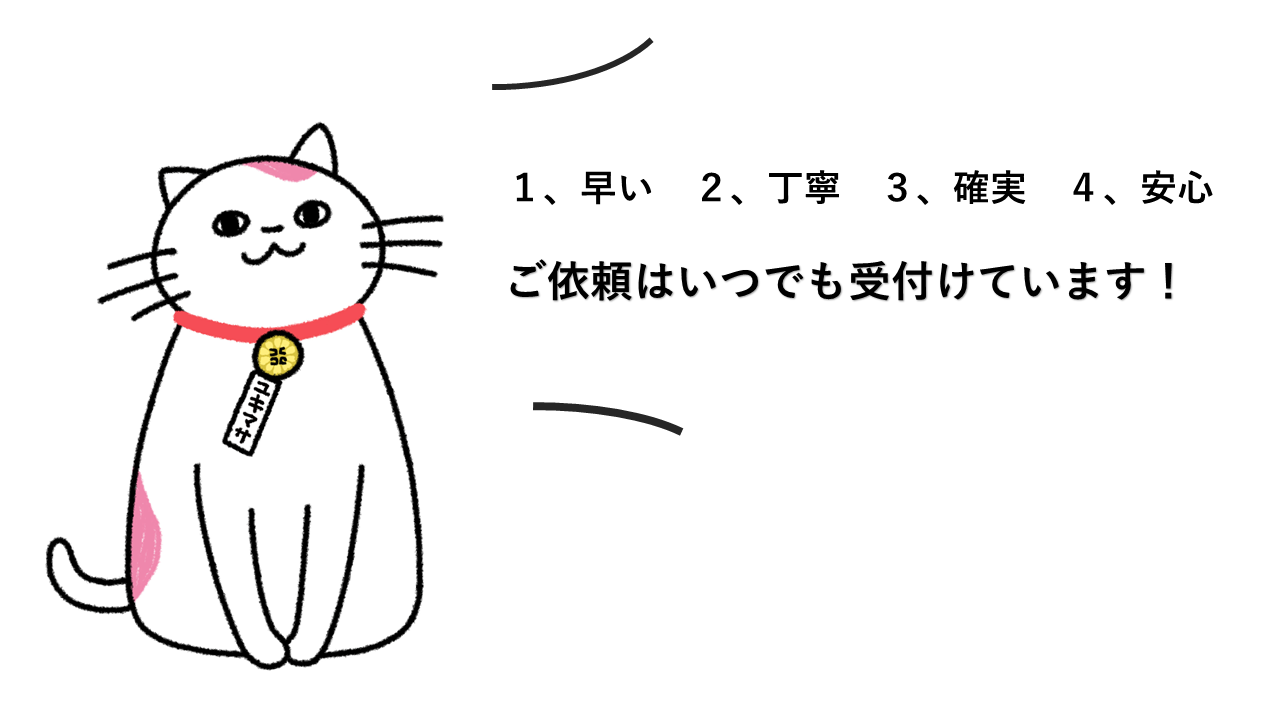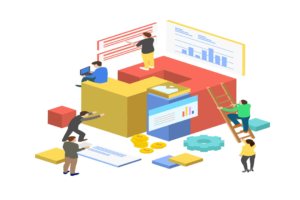個人とは異なり、法人の決算期は自由に決めることができます。
本記事では損をしない決算期の決め方について解説していきます。
(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)
目次
決算期のは自由に決めることができる
個人は12/31決算と決まっており、1/1から12/31までが1業年度となります。
しかし、法人の場合は、この決算期を自由に決めることができます。
例えば、8/31決算とすることもできますし、10/20決算とすることもできます。
また、既に会社設立後に決算期を決めたとしても、今の決算期を変更する事もできます。
節税効果を狙った決算期の決め方
例えば、3/10から会社設立し、同月の3/31を決算日とした場合、1期目が1カ月弱しかありません。
そのため、1期目2期目併せて24カ月の消費税免除期間をとれるところを、1カ月+12カ月で13カ月分しかとることができません。(⇒新設法人は消費税免除)
消費税課税額が1,200万円の場合、240万円の消費税免除されるところ130万円の免除しか受けれず、110万円のマイナスとなります。(消費税10%計算)
また、「青色申告の承認申請書」を提出しないまま1期目の決算をむかえると白色申告になってしまいます。
青色申告の場合、赤字計上した分は翌年以後7年間繰り越すことができますが、白色申告の場合は繰り越すことができません。(⇒会社設立後にする青色申告の届出)
500万円赤字の場合、500万円×30%(実行税率)=150万円の節税となったところ節税0円となり、150万円のマイナスとなります。(実効税率30%計算)
決算期を決める3つのポイント
上述した例は、最悪な決算期の決め方です。
こうならないためも会社設立後、一番有利な決算期を決めるための3つのポイントを下記します。
・設立1期目を極端に短くしない
・設立1期目をできるだけ長くする
・繁忙期を外す
青色申告の承認申請書の提出を失念しないためにも、設立1期目は極端に短くしないようにします。
例えば極端にいうと、10/25設立、10/31決算にすると中6日しかなく、失念する可能性は高いといえます。
消費税の免税制度を明一杯生かそうとすると、設立1期目はできるだけ長くすることが大事です。
また、できるだけ長くすることにより、決算時の手間や費用を先延ばしにするメリットもあります。
決算というものは、今後会社が存続する限り、毎年必ず発生します。
業務の繁忙期に決算対策に時間をとれないとなると、節税対策が不利になる可能性も高くなります。
また、決算時に税理士とじっくり話がしたいという場合も、税理士の閑散期6月~8月を狙うのも良いです。
大阪で開業・起業支援サポートを依頼する
いかがだったでしょうか?決算期の決め方についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る)
アカツキ法務事務所では、会社設立や創業融資サポートなどの起業支援、営業に必要な許認可や外国人の就労ビザの取得代行など行っております。
また、他士業の専門業務に関しましても広く提携を結び、サービスを提供させていただいております。
ご依頼・ご相談に関しまして、お気軽にお問い合わせください。(⇒お問い合わせする)